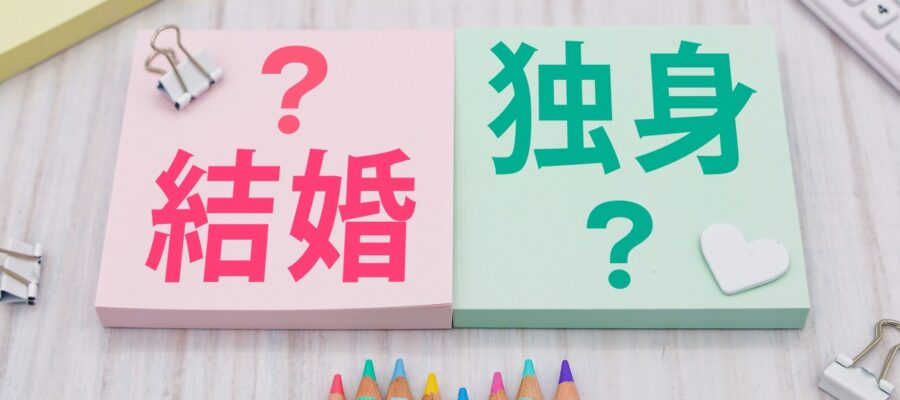「2026年4月から独身税が導入される」と、SNSなどで話題になっているようです。独身者のみが増税されることなどあるのか、疑問に感じている人もいるでしょう。
そこで今回は「独身税」のうわさについて、真偽を中心に解説します。
「独身税」の正体は「子ども・子育て支援金」
結論から言うと、独身者のみを対象とした増税は予定されていません。そもそも、「独身税」という名称自体が俗称です。正確には「子ども・子育て支援金」で、2026年度に創設が予定されています。
子ども・子育て支援金は、少子化対策にかかる財源を補うための制度です。全世代、医療保険料と併せて徴収されます。よって、独身者のみに課される税金ではありません。
子ども・子育て支援金が独身税と呼ばれる理由は、その使い道にあるようです。子ども・子育て支援金の使い道は、「子育て支援策の拡充」が中心となっています。子育てをしていない世帯には恩恵が少なく感じられることから、「独身税」と呼ばれているようです。
一方、上記の意見に対して、こども家庭庁は次のような見解を示しています。
●少子化・人口減少の問題は、日本の経済全体、地域社会全体の問題であり、こどもがいない方や子育てが終わっている方などにとっても、極めて重要な課題です。
●したがって、支援金を充てる給付を直接受けない方にとっても、少子化対策によって我が国の経済・社会システムや地域社会を維持し、国民皆保険制度の持続可能性を高めることは、かけがえのない重要な意義を持つものです。
●また、事業主の皆様にとっても、実効性のある少子化対策の推進は、労働力の確保や国内市場の維持の観点から、極めて重要な受益になります。同庁の試算によると、子ども・子育て支援金の創設により、支援金を充てる事業による0~18歳までの間の累計給付額は、子ども一人あたり平均約146万円に拡充されるとのことです。
子ども・子育て支援金の額は、医療保険制度・所得・世帯などで異なる
同庁によると、医療保険加入者一人あたりの全制度平均見込み月額は、次の通りです。
●令和8年度:250円
●令和9年度:350円
●令和10年度:450円ただし、個々人の厳密な拠出額は、加入する医療保険制度・所得・世帯の状況などによって異なります。例えば、医療保険制度別の加入者一人あたりの平均見込み月額は、表1の通りです。
表1
| 令和8年度見込み額 | 令和9年度見込み額 | 令和10年度見込み額 | |
|---|---|---|---|
| 被用者保険 | 300円(被保険者一人あたり450円) | 400円(被保険者一人あたり600円) | 500円(被保険者一人あたり800円) |
| └全国健康保険協会(協会けんぽ) | 250円(被保険者一人あたり400円) | 350円(被保険者一人あたり550円) | 450円(被保険者一人あたり700円) |
| └健康保険組合 | 300円(被保険者一人あたり500円) | 400円(被保険者一人あたり700円) | 500円(被保険者一人あたり850円) |
| └共済組合 | 350円(被保険者一人あたり550円) | 450円(被保険者一人あたり750円) | 600円(被保険者一人あたり950円) |
| 国民健康保険 | 250円(一世帯あたり350円) | 300円(一世帯あたり450円) | 400円(一世帯あたり600円) |
| 後期高齢者医療制度 | 200円 | 250円 | 350円 |
被用者保険の被保険者とは、「被用者保険に加入している本人」を指します。被保険者には被扶養者が含まれないため、「加入者一人あたりの平均額」よりも「被保険者一人あたりの平均額」の方が高くなる仕組みです。
なお、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、低所得者などに保険料の軽減措置が実施されます。また、国民健康保険では、18歳年度末までの子どもにかかる支援金の均等割額は、10割軽減されます。
独身者のみを対象とした増税は予定されていない
「独身税」は俗称で、正確には「子ども・子育て支援金」のことを指します。独身者だけに課されるのではなく、全世代から医療保険料と併せて徴収されます。ただし、子育てをしていない世帯には恩恵が少なく感じられることから、独身税と呼ばれているようです。
子ども・子育て支援金における負担額の全制度平均は、令和8年度で250円、令和9年度で350円、令和10年度で450円が見込まれています。ただし、厳密な額は加入する医療保険制度・所得・世帯の状況などで異なります。
出典
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A
<ファイナンシャルフィールド>
2026年から「独身税」が開始!? 独身を理由に「増税される」なんてことはあるのでしょうか?